俺のために、
一度、その町の問題を解決したり、それに伴って魔物を倒したりすることで、
それなりに腕が立つと認識されるのは当然と言えば当然だ。
再び何事かを依頼されるようになることもまた、珍しくも何ともない。
最強の剣を求めて旅を続ける中で実感してきたことだが、ウィルたちと同行するようになってからもそれは変わらなかった。
寧ろ、自分よりも圧倒的のお人好しの精神を持つ彼らは――その中には自身の姉であるミレーユも含まれるため、一概に悪くも言えないのだが――テリー以上に何かしらの困り事を解決してくれと頼まれることが多かった。
同行し始めてから「ついていけない」と何度思ったか知れないが、とてもそんなことを言える雰囲気でもないために、ただ溜息を吐いてやり過ごすのが常だ。
そしてその日も、例によって彼らは、所謂「人助け」をすることになった。
そこまで他人にかまっている場合か、と文句の一つでも言ってやりたくなるが、生真面目な姉に「すぐ済むから」と言われてしまえば、必要以上に彼らの行動を否定することはできなかった。
ある意味、魔物の巣窟に乗り込んで戦い、己の剣の腕を磨くことが人助けに繋がるのなら全部が全部悪いとは言わない。
しかし今回の依頼は魔物と戦うというよりも、どちらかと言うと「おつかい」の意味合いが強かった。
「離れている息子夫婦のところに物を届けたい」というとても単純なものであるのだが、頼んできたのはもう随分な年となっている老婆。
無碍に断ることもできず、かと言って長距離を歩いて物を届ける以外に、ほとんどやることはない。
腕の立つ彼らに頼んだのも、町の外にいる魔物と遭遇したときのことを考えてのことであろう。
しかし、この辺の魔物と戦うことはウィル達にとって赤子の手を捻るようなもの――と言うと
些か盛ったところもあるかもしれないが、彼らも相応の力をつけていることに嘘はない。
最強の剣士を目指す、と豪語しているテリーからしてみれば、これほど退屈なものはなかった。
そんな弟の胸中を察したのだろう、ミレーユからの提案は次のようなものだった。
―――今日の依頼は、そこまで大変なものじゃないから、ユナちゃんと残ってて?
たまには休憩も必要だと思うから。
何故ユナまで、と言おうとしたものの、最近彼女が少し疲れているのは傍目でも明らかで、黙った。
使える魔法はホイミとギラとメラ、辛うじてベホイミ、という有様である。にも関わらず、
「自分も役に立ちたいんだ」
と叫ぶや、テリーにしてみればまだまだな動きで、身の丈ほどもある剣を振るい、前線に出ていこうとするのだから見ていられない。
だが、チャモロに比べて満足に後方支援もできないことに後ろめたさを感じるのか、魔物の数が多いとき等の、所謂焦ったときの身勝手な行動は、日に日に増えていた。
その分、ユナの怪我する確率は高くなったし、彼女の疲労が重なっていっているのも明白だった。
自業自得以外の何物でもなく、もっと自分の立場を弁えていれば、まだ楽にできる部分もありそうなものであるが。
彼女のあまりに無茶な行動を放置しているのも落ち着かず、庇ったり助けたりしたことは数え切れない。自分以外に、ウィルやハッサンによるフォローまで数え始めると余計にだ。
何度怒って喧嘩になっても、結局根本的なところは変わらず、最終的に同じような振る舞いをして見せるユナには、ほとほと手を焼いていた。
先日も本気で怒ったテリーと派手な喧嘩を繰り広げ、会話数が激減しているところだ。
「ユナも疲れてるし、この依頼はテリー、あんまり乗り気じゃねえんだろ? なら休んでろって、ここは俺たちに任せてよ!」
「そーそ、それにユナと仲直りするのに丁度いいんじゃなーい?」
とは、ハッサンとバーバラの意見。
テリー自身(バーバラの意見は真っ向から無視していたが)、乗り気でないのも事実である。
丁度、使い続けている剣の手入れをしたいと考えていたところでもあったしと無理矢理な理由を自分の中に落とし込むことで、今回は残ることに決めた。
ユナは、テリーと二人きりになることを避けたいと思ったのか、前日まで「大丈夫、行く」と意固地になって言っていたものの、依頼をこなす当日になった朝に起きてすら来なかった。
やはり疲れていた手前、”休んで良い”という気の緩みがあったせいであろう。
かくして、ユナとテリーは共に宿屋に残ることとなった。
依頼で行く先は半日かかる距離であるため、事実上丸一日はユナと二人で宿にいることになる。
(しかし、よく寝るな……)
剣の手入れのために暫く部屋にこもっていたが、昼過ぎになっても隣の部屋から物音一つしないことに不信感すら覚え、テリーはユナの泊まる部屋へと様子を見に行った。
ドアをたたくと、暫く無音であったが、床がきしきしと鳴る音がかすかに聞こえ、ややあってドアノブが回った。が、それきり、誰も出てこない。
「……?」
テリーは首を傾げ、細く開いているドアを押した。
真っ先に顔を出したのは、青い、玉葱型の軟泥状の魔物――スライムのスラリンだった。
「お前……」
ピキー、と鳴きながら、テリーの足にすり寄ってくる。子供の頃を思い出した一瞬口元が緩む。
恐らく、スラリンがジャンプして何とかドアノブを回すまではしたものの、ドアを引くことは出来なかったのだろう。
部屋の奥へと視線を投げると、ベッドの上に人一人が潜り込んでいるであろう膨らみがある。
「お前の主はまだ起きないのか」
「ピキ」
言葉の意味はとれないテリーでも、スラリンの今の一声が肯定であることは、想像に難くなかった。
しばらくベッドの膨らみを遠目に眺め、沈黙。やがて踵を返すと「ピキ」とまた一声。
「寝ているならわざわざ起こさなくてもいいだろ」
「ピキピキィ……」
「傍にいてやるのは俺じゃなくてお前がやればいい。その方が喜ぶだろ、あいつも。それに俺はこんなところにいるほど暇じゃ――」
そこまで言い切ってから、スラリンの言葉は分からないのになぜこのような言い訳がましい言葉が延々と零れてくるのか、と真顔になる。しかしスラリンは明らかに引き留める様子で自分の周りをぴょんぴょん跳ね回っていた。
テリーの眉間の皺がどんどん深くなる。
「……いてやれって? 傍に?」
今度は確認する。言葉の意味は合っているのか、と。
「ピキー!」
清々しいほどのYES。テリーは無言で額に手を当てる。
ユナのことが嫌いだから、すぐにここを去りたいというわけではない。
心配していないのかと言われれば勿論否。
喧嘩をしたのだって、怪我しないためにもっと後方支援に徹しろ、という心配しての意見と、それに対し「うん」と頷かなかった彼女との意見のぶつかり合いが元だ。決して初めてのタイプの喧嘩ではない。
もっと言うならウィルたちと出会う前、二人で旅をしていた頃から、いっそ日常茶飯事とまでいえるほどに繰り返した口論であるが……。
(………)
解せない、と思った。かつてユナが熱を出したときは何だかんだ傍にいた。寝付くまではいる、と。
だが今回は――
(……何だ。この、居心地の悪さは)
居心地の悪さだけではなかった。無性に腹が立つ。
こんなに寝入ってしまうのは、それ相応の休養を体が欲していたことと同義である。
空腹などで目覚めるのも体の信号の一つ。女にしては、ユナはそこそこに食べる。
しかし事実、彼女は朝食なんて食べていないし、起きる兆しもないのでは昼食も抜くことになるだろう。
空腹を満たすことよりもまずは眠って体力を回復させるのを、体が最優先にしているということだ。
(……俺たちの中に、こいつほど消耗してる奴なんかいない)
ユナは、必死すぎる。元々剣の才に秀でているわけではなく、魔法に関しても同様だ。
本来、旅に出るにはあまりに実力が伴っていない。人一倍努力しているのは知っている。
だが、やはりそれでも追いつけないものは追いつけない。
人一倍努力すれば必ず報われるなんて、嘘だ。努力しても個人の限界値がある。
それを越えようとしたらどうなってしまうのか。
黙りこくったテリーの顔を、よく見ようと思ったのだろう。スラリンが足にまとわりついてきた。
プニプニとした独特の感触に我に返ると、おもむろに手でスラリンを剥がした。
そして、歩みを進める。部屋の外へ。
「ピキー!!」
「傍にはお前がいてやれ」
手をひらりと振って、足早に部屋を離れる。
自分の部屋に戻ろうとしかけて、やめた。町の方へと繰り出すことにする。
自分の悪い癖だ、と自身に対して舌打ちをした。思考を回し始めると、止まらなくなる。
彼女に関することとなると、とくに。
再会できると思っていなかった。そして再会の仕方はある意味最悪だった。
魔物――デュランの手下として戦う自分の姿が、到底誇れるものでないことくらい分かっている。
それでも、力を求めることをやめられなかった。今でもそうだ。
二人旅をしていたとき、自分の傍から彼女がいなくなると、何度だって自分の無力さを呪った。
かつて、姉を助けることの出来なかった自分と同じ悔しさを覚えて、強くなりたいと心から願った。
『詭弁だな。心なんかで魔物は殺せない』
伝説の剣があると言われた氷の洞窟で、ウィル達に会った際に投げかけた言葉は、はっきり覚えている。
『思うだけじゃどうにもならない! 力がなければどうにもならないんだ!』
自分の中にあった葛藤を、たまらず吐き出した。それから間もなく、自分は闇に飲まれたのだ。
魔物に、魂を売ったのだ。まさか、あのウィル達の中に、死んだとばかり思っていたユナが、そしてかけがえのない姉であるミレーユがいるなんて、考えたこともなかった。
闇にとらわれた後、ウィル達に救われ、そして共に旅に同行することになったときも、ユナは笑って言ったのだ。敵となっていたテリーの、闇の力に溺れたことも、まるで気にせずに。
『オレはテリーの仲間だろ?』
(……どうだかな……)
実際に言われたときも、「さあな」と、つれない返事をしたような気がする。
カウンターに両肘をつき、組み合わせた両手に顎を乗せた状態で、ぼんやりと考える。
町に繰り出してきても、どこに行くのも気が引けて、結局腰を落ち着けたのは酒場。
昼間から飲んだくれるわけにもいかないし、そういう気分でもない。
テリーの目の前に置かれた杯の中で揺れるのは、少しの甘さが舌に残る、風変わりなお茶だ。
ここの酒場で特別に作っているらしく、女性にも人気との説明を受けている。
ふ、とテリーが目を細めた。
自分がもう少し素直になれば良いことくらい、分かっている。
例えばユナに、前線に出るなということを、心配しているからとか、拙い魔法でも後方支援は充分にできているとか、言葉にすればまだ言うことは聞くのだ。きっと。
……だが勿論、テリーはそんなことは言えない。
どうしても、長年かかって形成されたひねくれた性格は、「足手まとい」であるとか、そんな傷つけるような言葉しか形作ってくれないのだ。何とも、じつに何とも面倒なことに。
「お兄さん、眉間に皺、すごぉい」
猫なで声が聞こえて、妙に距離をとめて隣に女が座ったことに気づく。
幸い顔が良い彼は、こうして女が寄ってくることに慣れていたので、驚きはしなかった。
ゆえに、目さえ向けない。
「ねえねえ、この後、暇じゃなぁい?」
「悪いが他をあたれ」
「あ、やっぱり?」
えっ。テリーは目を丸くした。こういうすり寄ってくる女は、大抵面倒くさくしぶとい。
一言二言冷たい言葉を吐いても、「かっこいい」と褒められたり、「そんなこと言わないで付き合って」と纏わりつかれることが圧倒的に多いのだ。
首を回してみれば、てへ、と笑うのは、やはり知らない女だ。
微妙に声が似ていたし、この悪戯っぽい笑顔は、若干バーバラに通ずるものがある。
すなわち、テリーが本来、苦手とするタイプだということだ。
「お兄さん、すごーい悩んでるもんね。恋煩い?」
「関係ない」
変に猫を被らない辺り、酒場にいる女にしては珍しい。
しかし馴れ馴れしいという面で言えば同じだ。
一人旅をしていたときなら適当に相手をして、資金を稼ぐために女と寝るに至ることは多々あった。
しかし今はウィル達と旅をする身であり、資金を一人で工面する必要もない。
となれば、面倒に巻き込まれるのは御免だった。杯を手に取り、一気に茶を呷る。
時刻も徐々に夜に近づいてきていて、酒場に人が溢れる頃だ。さっさと出よう。
「損してるよねぇ、お兄さんみたいな性格の人って」
だが、心底呆れた、といった様子で吐かれたその言葉を、無視することができなかった。
空になった杯をマスターに返しながら、「何だ」と問い返す。
「いちいち揉めてるっていうか、多分、今日宿屋に残ってる女の子と喧嘩してるんでしょ?他の旅のお仲間さんたちはおばあちゃんの依頼を受けてくれてるのも知ってる」
「おばあちゃん……?」
依頼してきた老婆のことを思い出す。
彼女はそっと肩を竦めた。
「私は、見ての通り水商売で稼いでるんだけど……実は、両親がいなくてね。病気で早くに死んじゃって、身寄りもなくて。そこを、おばあちゃんに助けてもらったんだ。ただで一緒に住んで良いって言ってくれたんだけど、さすがにそれじゃ肩身が狭いし。おばあちゃんの力になりたくて」
でも、と困ったように首を傾げる。
「あの、君たち旅人さんに依頼したこと、私がやってあげられたら良かったんだけど、ああいう両親だから、私もそこまで体が強くないのね。だから、魔物と戦ったり、無理に遠出するわけにもいかなくて。だから、君たちが引き受けてくれたっていうのをおばあちゃんから聞いて、すごく嬉しかったんだ」
そして彼女は、依頼先に出発してしまう前に、ウィル達にお礼を言いにいこうと考えて朝の早い時間に宿屋にやってきたらしい。
そのときに、テリーとユナが残るとか、残らないとかの話を聞いたようだ。
テリーもかなり臍を曲げていたのでさっさと部屋に籠もってしまったため知らなかったが、万一自分たちがいないときに町で何か困ったことが起きたときは、宿屋にテリーとユナが残っているからその二人に頼るように、とも、併せて伝えられていたと言う。
テリーとユナの喧嘩に関しては、お喋りな少女が頼んでもいないのに聞かせてくれたようだ。
「ぎすぎすしてるかもしれないけど、本当は仲良しだから頼って大丈夫」と。
「酒場来たときに、あ、お礼言えるーって思ったんだけど……お兄さん、ずっと怖い顔してるからね」
悪気はないだろうし、根は良い娘なのだろう。
だがバーバラほどではないかもしれないと言えど、相当にお喋りだ。テリーはため息を吐く。
「余計なお世話だ」
「ほら、そういうところ」
間髪入れず指摘され、眉間の皺が深くなる。
「ちょっと会話しただけで分かった気がするけど、お兄さん、言葉を素直に言うのはめちゃくちゃ苦手なタイプでしょ? もしかしてその女の子との喧嘩っていうのも、原因、そこにあるんじゃないの?」
本当の原因と言えば無茶をするユナにこそあるのだが、大喧嘩にまで発展した要因に自分の性格が関わっていることは否定できない。
無言は肯定と理解したか、彼女はにやりと口角をつり上げる。
「もしその性格直せないならさ、せめて態度で示してあげたら?」
何を、と目で訴える。
「何で喧嘩したのか分からないけど、もしお兄さんが居心地悪く感じてるなら、仲直りしたいんですよーっていうのを、態度っていうか、行動で。だって、みんなずっと一緒に旅をしてきたなら、言葉にしなくてもそれくらい読みとってくれそうなものじゃない?」
がたりと音を立てて、隣から立ち上がる。目が入り口の方に向いていた。
テリーも彼女の視線を追いかけてそちらに目をやると、一人の男が視線を巡らせながら入ってくるところだ。どうやら、本日の彼女の客らしかった。
「おばあちゃんの依頼を聞いてくれたお礼だと思って、ちょっとしたアドバイス。よければ役立ててね」
慣れているのか、器用に片目を閉じて見せると、腰を艶めかしく振りながら酒場に入ってきたばかりの男に駆け寄り、肩をきゅっと寄せて色っぽく笑いかけていた。
あれが彼女の仕事モードらしい。
マスターが、もういいんですか、と声をかけてくるのに軽く手を振ることで応え、テリーは酒場の外へと足を向ける。
酒場の外は案外暗くなってきていて、空が夜の闇に包まれようとしているところだった。
思ったよりも酒場に長居してしまったようだ。
頭を振り、帽子を脱いで己の銀髪をがしがしと掻き乱す。舌打ちが漏れる。
鞄の中をまさぐり、中に入っていたスライムピアスを取り出すと、沈みかけている夕日に翳してみた。
申し訳程度にスライムが彩りを変える。
暫くそうしていたが、テリーはスライムピアスを鞄の中へとまた押し込むと、早足で宿屋へ帰還した。
扉を開くと驚いた様子で此方を振り返った宿屋の主人が「おかえりなさい」と笑う。
つかつかと歩み寄れば気圧されたように、主人は少し後ずさった。端的に、告げる。
「頼みたいことがあるんだが」
* * *
無音の、水の中にいるような感覚から、突然体が浮き上がって水面に顔を出す感覚と似ていた。
体に何かが絡まっているように動きにくく重い。視界に最初に映ったのは木でできた天井。
数回瞬いて、霞む視界を少しでも鮮明にしようとする。
鉛のように重い腕を動かして、何とか起き上がる。
すると、自分の体に乗っている、青い軟泥状の生き物が認識できた。
そっと手を差し出し、柔らかく、少し冷たい体を、よしよしと撫でてやる。
何となく窓の方に目をやって―――あれ、と思った。時計に視線を投げてみれば、真夜中だ。
「……夜? ……ってことは、オレそんなに寝てないのか?」
目が覚めたのだから当然朝だと思っていたのだが、思ったよりもすぐに意識が浮上したようだと首をひねり、肩を回して―――
「あでででで!?」
ぼきぼきぼきっ、といっそ清々しいほどの音が鳴って悲鳴を上げる。何だ!?と思いながら瞳を揺らす。体が固まっていた。
スラリンを起こさないように布団を剥ぎ、そっとベッドから降りる。体が重い。怠い。
何気なく自分の手の甲を、己の首にあてる。が、自分で自分の体温を確認しても、よく分からないのは当然のこと。
ドアを開けて、ウィル達の姿を探す。しかし宿屋のどこにも姿がない。
気になったといえば、テリーの荷物だけが部屋に残されていた。
とすれば、ウィル達は何らかの事情で宿屋からはでていることになる。
―――ユナちゃんは、テリーと待ってて?
ミレーユの言葉。
他にも、ウィル達に残ることを勧められたことを思い出す。
喧嘩しているテリーと二人きりになることが嫌で、大丈夫だ、と必死に訴えたことも。
じわじわと記憶がよみがえってきてから、じわじわと自分の顔が引きつり始めるのを感じた。
(まさか……オレ……)
そのとき。
ふわり、と何やら甘い香りが漂ってくることに気づく。きゅう、と鳴るのはユナの腹だ。
現状を理解するために必死に回していた頭が、突然、「空腹」であることを異常すぎるほどに主張してくる。腹の虫もどんどん五月蠅くなった。
しかし疑問も共に浮上する。この真夜中に、宿屋の主人が料理を準備するはずもない。
ただ香りは明らかに、食堂の方からだ。どういうことだろうと暫く右往左往していたが元々それなりに食べるユナは、五月蠅い腹の虫を無視することなど到底できない。体は食べ物をこんなにも欲しているのだ。
階段を下りていく最中に、膝が少し笑っていることや、満足に足が上がらないこと、腰から一気に砕けそうになることから、自分の中で曖昧だったものが確信に変わっていく。
自分は、予想だにしないほどに長い時間眠っていたようだ。
転がり落ちないように壁に手をつきながら、ゆっくり一階へ下りる。
宿屋の入り口の灯りも消えており、カウンターに主人の姿もない。
真夜中なのだから当然か、と息を吐く。こんなに体がガタガタの状態で、あまり面識のない人に会うのは避けたいと思っていた手前、良かった。しかしそこで足が止まる。
では、食堂の方から香ってくるコレは、何だろう。
主人が明日の朝食を早めに準備しているのだろうか。
真夜中に体の動きがぎこちない宿泊客が、匂いに誘われて食堂にやってきたら……。
あまりの格好のつかなさに眩暈がし、やはり部屋へ引き返そうかと思った矢先、「くぅ」と抗議するように腹が喚いた。
「う……」
いい加減、空腹も限界だ。ここで空腹のあまり倒れた方が、もっと格好がつかないだろう。
心を決めて、ユナはよろつく足で食堂へと再び歩き始めた。
仕切られている入り口のカーテンを細く開き、顔を覗かせる。
この宿屋の食堂は、すぐ横にキッチンが備え付けられている。
宿屋の主人がそこで料理を作り、出来立てを振る舞ってくれるのだが、キッチンに立っている背格好は、ユナがもっと見慣れているものだった。
フライパンを持っている彼が上体を捻り、此方に視線を向ける。
「寝坊助」
無関心そうに向けられたアメジストの瞳を細め、短く言うと再び火元へと向き直り、手を動かし始める。
予想していなかった状況に、ユナの思考が停止する。カーテンを半開きにしたまま固まっていると、再び彼が此方を振り向いた。そして、顎でしゃくり、すぐ近くの席を示した。
そこにはナイフとフォークが置かれており、成程料理の準備がされている。
他の座席にもないので、しっかり一人分の準備だ。座れ、と言っているらしい。
ユナはどぎまぎしながら、「お邪魔します……」と恐る恐る食堂に足を踏み込む。
「ん」と短い返事があった。強ばった体を何とか動かして、示された席までやってくると、音を立てないように座る。ちらり、と料理をする彼の様子をうかがった。
フライパンからはジュウッと音が鳴っている。
「体の調子は」
目を向けないまま尋ねてきた。両肩を跳ねさせ、そしてすぼませ、小さく頷く。
「大丈夫……ええと、結構、寝たみたいだから……」
「そうか」
沈黙。二人の間を支配する音は料理の油が熱されている音ばかりだ。
まだ怒っているのかな、とユナは更に小さくなった。
元々自分が、彼らが魔物と戦いになる度に迷惑をかけていることくらい、本当は分かっていた。
役に立てないことが、何より焦る。皆優しいので、充分役に立っている等と言ってくれるが、優しさを取っ払った結果の言葉だとどうなるのか。
一番自分をかばってくれている彼が、苛つくのも当然である。
「あの、さ、テリー……その……」
「いい」
謝ろうと口火を切ったが、それは他でもないテリーによって言葉を遮られる。
フライパンを持ち上げ、横に置いていた皿の上に作っていたものを箸で乗せながら言った。
「お前が怪我しないなら、いい」
ユナが驚きに目を見開く。
視線の先の彼は、作り終えた料理を乗せた皿を二つ持って振り向いた。
彼女の前に置き、再びキッチン台に向かうと、今度は使い終えたフライパンをざぶざぶと洗い始めた。
ユナの前に置かれたのは、薄く伸ばされた生地に、この辺で採れるフルーツとココナッツクリームを一緒に乗せたもの。そして、今の今まで作っていたのだろう、ほかほかと湯気を立ち上らせる黄金色のオムレツだ。横に、小さなトマトもおまけとばかりにつけられている。
「怪我しないならそれでいい。だから、お前も怪我しないように俺たちの役に立て」
言葉を並べ、それからテリーが此方を向く。
オムレツとデザートを見つめて固まっている彼女を面白くなさそうに眺め、一言。
「食わねえなら片付けるぞ」
「た、食べるよ! 食べます!」
慌ててフォークとナイフを手に取り、大胆にオムレツの真ん中にナイフを入れる。
すると、中からトロリと流れ出したのは、若干緩い卵と、溶けだしたチーズだ。
一口大に切って口の中に押し込んでみると、チーズとは別の独特の甘み、それに卵の食感が絶妙に絡んでいることが分かった。
ここまでの料理どころか、まず食べられるかどうか怪しいものしか料理できないユナは、こんなところでも自分の無力さを知った気がして、眉を下げた。
「……例えば。俺が怪我をして満足に剣が振るえなくなったとするだろ」
無力さを知っても、空腹には勝てない。
もぐもぐと必死にオムレツを腹に詰め込んでいれば、ぽつぽつとテリーが語り始める。
ユナは、それに耳を傾けた。
「俺はそんなに魔法が使えるわけじゃあない。…後方支援なんか、俺が苦手とするところだ。それでも指くわえて戦いを見てるなんて俺にはできない。とすれば、俺は振るえもしない剣を必死に持って、必死に前線に出ようとするかもしれない。それで死んだっていいってな」
「だ、だめだよテリーが死ぬなんて!」
死んだっていい、という言葉は流石に聞き捨てならず、慌ててユナが叫んだ。
すると、振り返ったテリーが、くっと口角を歪めて見せる。そこで、ユナもはっとする。
彼は水を止め、キッチン台にもたれて軽く肩を竦めて見せた。
「……そういうことだ」
オムレツを食べる手を止め、俯く。
「何てことはない。あいつらも…俺も、思ってるのはそういうことだ」
「……うん」
「分かったな」
「うん」
「よし」
満足そうに頷くと、くるりと体を回してまた、水を流し始める。
そして、水音に紛れて聞こえない程度に、小さく、小さく、言葉を紡ぐ。
「え?」
「何でもない」
それより、と声量を戻して。
「お前も女だ。これくらい作れるようにはなっておけ」
「は、はあ!? いや、えっ、これはレベル跳ね上がりすぎ……」
くつりと笑う声がして、ユナがおろおろしながらもテリーを見やる。
彼は、口元に手をやって、喉を鳴らしながら笑っていた。
悪戯小僧のようなその様子はなかなか見ることのない表情で、思わずぼうっと見惚れる。
「冗談だ。それに、姉さんの料理を手伝ってるせいか、前よりは様になってきてると思うぜ」
自分が「うん」と言ったのは、果たして声になっていたのかいないのか。
ともかく、はっきりと頷いたときに、自分の顔が非常に火照っていたのは、言うまでもない事実だった。
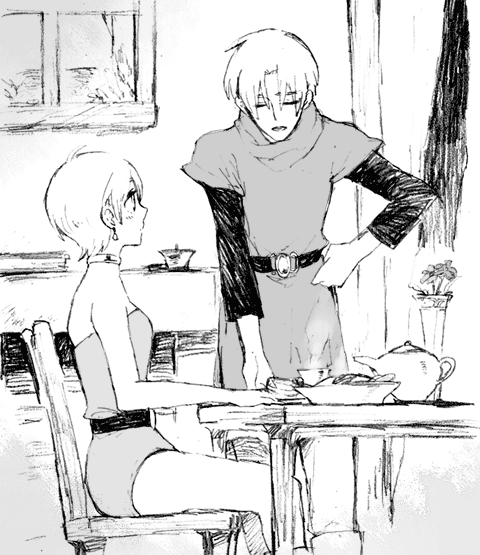
* * *
翌日の夕方に、ウィル達は帰ってきた。実際に町そのものに帰ってきたのは、もう少し早い時間であったが、先に老婆の家に依頼達成との報告をするべく寄っていたため多少の時間がかかったようだ。
「ユナさんの調子はどうですか?」
チャモロが荷物を置きながら、本を読んでいるテリーに問いかける。
ウィル達も同じことを思っていたようで、気になるとはっきり顔に書いてあった。
「ああ、あいつなら……」
「ただいまー!」
聞こえてくる大声。階段を駆け上がってくる音がして、部屋の扉を派手に開けるのは、噂の彼女。肩にはスラリンを乗せていて、両手には袋を提げている。
「あ、ウィル達、やっぱり帰ってたのか! 外にファルシオンがいたからさ! おかえり!」
「ピキー!」
「おう、ユナ! 随分顔色が良くなったじゃねえか!」
血色の良い顔に全員が安堵する。しかし、続けて浮上するのは、ユナが持っている袋への疑問だ。
傍目でも結構な量が入っていることは分かるし、一体一人で何を買ってきたのか。
一応、旅の資金に関してはそれほど困っていないし、なくなったところで稼ぎようならいくらでもある。
勝手に出費したことに怒ることはないのだが……。
「なあユナ、どうしたんだ、それ?」
「これか? えへへ、馬車の中に積んである食料とか、薬草とか……諸々足りなくなってきてるなーって思ってたからさ。宿屋にいても暇だし、ちょっと買い出しに行ってたって感じ」
ウィルの問いかけに少し袋を掲げて見せ、中を覗くとたしかに旅に必要とするものばかりが入っていた。怪我をしたりすれば馬車の中に押し込まれることは少なくない身だったからこそ、誰よりもいち早く気づいたのだろう。
充分な力を蓄えつつある彼らは、最近は魔法頼みであるところもあったし、そうした薬草等の管理が杜撰になってきていたことは否定できない。
「って、宿屋にいても暇だしって、テリーとは何もなかったの?二人で一晩、屋根の下だったのに~?」
わざとらしくからかってくるバーバラに顔を赤くし、大きく首を横に振る。
「何てこと言うんだよ、バーバラ! オレは別に……」
「ピキピキィ」
「えー! 何何、スラリン?」
「ああもう、バーバラもスラリンもやめろってばー!」
賑やかに騒ぐ彼らの様子を眺め、本を閉じたテリーは頬杖をつき、やれやれと見やっていると、傍にそっと近寄ってくる存在があった。
「その様子なら、仲直り、できたみたいね?」
ミレーユの、何でもお見通し、と言った口振りには、かなわない。
少し吐息を漏らしてから、控えめに頷いて見せた。しかし少し渋面を作って、姉を見上げる。
「姉さんはお節介すぎるよ」
「あら、そう?」
「今回の依頼をしてきた婆さんの家にいる娘に、妙なこと吹き込んだだろ」
「ああ……言われてみれば、バーバラが言っていたような気もするわね」
「そう仕向けたのは、姉さんじゃないのか?」
真っ直ぐに姉を見つめた。
あの、老婆の世話になっていると言っていた女は、嫌にしっかりと事情を知っていたような気がする。初めは随分聡い女だと思ったものだが、時間が経つにつれていくら何でもおかしいと思った。僅かしか喋っていないのにテリーの性格に難があることも随分はっきりと明言していたし、初対面にしてはできすぎている。
お喋りな女の子、と言われて咄嗟にバーバラだと思ったが、ミレーユもそこにいたはずだ。噛んでいないはずがない。
エメラルドの瞳と、アメジストの瞳がぶつかって数秒。思わず世界中の男が落ちるであろう微笑を、優雅に浮かべて見せた。蜂蜜色の髪が波を打つように煌めき、揺れる。
そして、一言。
「でも助かったでしょう?」
やはり、かなわない。
弟が唸りながら視線を外すと、ミレーユが楽しげに笑う声が聞こえてきた。
バーバラやハッサンに質問攻めにされているユナを見て、微かに口元が緩む。
馬車の中にある荷物をすべて把握している仲間など、そうそういない。
だから、ユナはユナのできることをしているのだ。
今朝だって起きるなり、「ちょっと買い物」と言って飛び出していくのだから、テリーだって驚いた。
すべてに秀でている必要はない。テリーとて、最強の剣士を目指していて剣の腕に秀でていても、ハッサンのように家を建てることはできないし、ミレーユのように占いで未来を見通せはしない。
「て、テリー! 助けてくれよー!」
一人でかわすには限界が来たのだろうか。ユナが必死にテリーに向かって叫ぶ。
が、そのとき、ユナは見た。見て、一瞬、自分の中で時が止まったようにさえ感じた。
穏やかに微笑むテリーが、本当にその一瞬だけそこにいて、次には自分のすぐ傍にきてハッサンとバーバラに適当なことを言って散らしてくれる。
ミレーユも加わって、ハッサンとバーバラをユナから引き剥がしてくれた。それらを眺めて、くすくすと笑っているウィルとチャモロ。
テリーが、隣にいるユナに対して。
「分かっただろ」
笑って、そして、また、顔を背ける。背けながら、その手をユナの頭に乗せて、雑に撫でた。
「ユナはここにいて、いいんだ」
〝ここに、いてくれ〟
「――うんっ」
喚く彼らの中でユナは、テリーの後ろに隠れて避難していた。
声は精一杯笑いながら、恥ずかしくて真っ赤になった顔を隠すときと同様に腕で顔を覆いながら、俯いた。
彼女の緩みきった口元、浮かべられた淡い笑顔の頬に、涙が伝ったことは、きっと、誰も知らない。
気づいてしまった声。
それが、水の音に紛れて聞こえなかった声と結びついたのは、多分、自惚れなんかではないと、思う。
fin.
「トト」様より、テリー&ユナの小説頂いたので自慢させて下さい・・・!!
わーーーー!!!わーーーーーー!!!!ありがとうございます!!!
ほんとうに素晴らし過ぎる小説!!!!わーわー!!!めちゃくちゃ面白かったです!!!!
何度も読み返してます あああああ……ほんとにすばらし過ぎてお金払いたい……;;!!!
あああああ・・・テリーかっこいい・・・;;!!(勝手に挿絵描いちゃってすいません)
本当にありがとうございました!!サイトにまたお宝が増えました・・・;;!!!
|