| 「おい、ユナ起きろ。サンマリーノだぞ」 ・・・・・・? 懐かしい、自分を呼ぶ声。寝ぼけ眼のまま目の前の人物を見つけると、また懐かしい顔。 上半身を起こすとようやく思考が動き出した。 どうやらここはサンマリーノの宿屋らしい。 開かれた窓からは太陽の光が降り注いでいた。 「ごめん・・・またテリーに任せちゃって・・・」 「別に良い。それより靴を買うんだろ?オレは色々回って夕方頃に酒場に行くから何かあったら来い」 それだけを言って部屋から出ていった。 ユナは顔を洗って、荷物の整理をしようとカバンを空ける と ムワァ。 汚臭が辺りに充満した。 「うっわ!くっくせえ!!」 慌ててカバンを締める。有る程度匂いは収まったが残り香もまた凄い。 水浸しになった上、半年間ほったらかしにされていたカバンだ。どうなっていてもおかしくない。 「スラリン・・・こんなカバンに入ってもらっててごめんな・・・」 ベッドの上のスラリンはユナの気持ちも知らずベッドで眠っていた。 窓を開けて気合いを入れると再びカバンを空けた。 結局、無事だったのは少しのゴールドに、ヒックスから貰ったスライムピアス、 ルドマから貰った魔導士のマントと服だけだった。 さすがに高くて良い物は違う・・・でもちょっと匂うけど・・・。 宿の裏の川で洗濯すると、部屋のベランダにマントと服を干した。 そして仕方なく、ユナはドレス姿でスラリンと共に町に出た。 防具屋に入って足にぴったり合う革靴を買い 旅に必要な衣類や道具を買ってカバンも新調した。 髪の毛も散髪屋でいつものように短く綺麗に切りそろえて貰う。 それから宿に戻り、ベランダに干していた服を取り込んだ。 まだちょっと匂いが残っているがこの際仕方がない。 慌てて着替えると幸いこちらも無事だった大きな剣を背負って 夕暮れ近いサンマリーノへと繰り出した。 ガラスの靴や今まで来ていたドレスを売ったりなんたりした後で、急いで酒場に向かう。 港への通りには色んな酒場がひしめいていたが テリーの行きつけの酒場は聞いていたので看板を頼りに店に入った。 「いらっしゃい」 お客の呼び鈴にマスターが気付いた。 「聞いてくれよテリー!ドレスとガラスの靴、凄い高値で売れたぜ!」 入るなりテリーに声を掛ける少女に客の視線は釘付けになった。 客の視線に思わず言葉が止まる。 「オイ、みろよあの子・・・」 「くくく、あんな体であの剣を装備してるつもりなのかねぇ」 く・・・やっぱり噂されてる・・・。だから酒場は嫌いだ。 「あんな奴らの言うことなんか気にするな」 「いいんだ、どうせオレなんて・・・」 ユナのマントからもぞもぞとスラリンが姿を見せると 男どもは面食いながら別の話題に切り替えていた。 「マウントスノーって言う所だろ?これから行く所」 ユナの言葉にテリーは頷く。 「今度こそ見つかるといいな。最強の剣」 「そうだな」 二人の会話に聞き耳を立ててしまっていたマスターが 「テリー君。もしかしてこの子があのユナちゃ・・・」 「テリー!」 言葉は甲高い声に遮られた。 店の奥からバニーガールが出てきてテリーに駆け寄ってくる。 パーマをあてた金髪の、スタイルの良い美女だった。 「ビビアンか。久しぶりだな」 テリーが言い終わるか終わらない内にビビアンは座っているテリーの後ろから抱きしめた。 をわ・・・っ!! ユナは慌てて背を向けた。 「どうしたんだ急に・・・」 テリーは慌てて振り切る。ぽたぽたとテリーの体に涙が伝っていった。 「だって・・・ラスって人が言ってたの・・・ テリーは海に飲まれて帰らぬ人となったって・・・だから・・・っだからアタシ・・・」 うっうっと嗚咽しつつ顔を両手で覆っている。 テリーはラスの事を思い出していた。帰らぬ人って・・・あいつ・・・。 「バカ。オレがそう簡単に死ぬ訳ないだろ」 側で泣き伏せるビビアンの頭をぽんと軽く叩いた。 ようやく落ち着きを取り戻したビビアンは安堵のため息をついて 真っ赤な瞳で恥ずかしそうに笑う。 ユナはその光景になす術もなく固まっていた。 そっか・・・そうだよな。やっぱりテリー、オレの事何とも思ってないんだよな。 分かってた事なんだけどさ。 心の中で急にそう悟る。 だってもし、オレの事気に掛けてるとしたら、もっと他の人と違った反応をするはずだから・・・。 テリーのバニーガールに対する行動はまるで自分と同じような物で・・・ いや、むしろ優しい・・・。 ふわりと長い金髪がユナの腕を撫でる。それと共に甘い香りが漂ってきた。 花の香水の良い香り・・・。 カタ・・・。 一つ向こうの椅子に座り直し、二人から距離を取った。 「テリー、もしかして、この子・・・?」 感動の再開に浸っていたビビアンが、やっとテリーの隣にいる少女に気付いた。 「ああ、こいつはユナだ」 紹介され、ペコリとユナは頭を下げた。 「えっ、この子が・・・ユナちゃん・・・?」 「初めまして、ユナです」 「あっアタシはビビアンよ。この酒場に努めてるバニーガール。テリーとは昔からの顔馴染みなの」 まだちょっと赤い瞳で愛想良く笑ってくれる、ユナもぎこちない笑顔を返した。 「そうだ、あの・・・テリー。ユナちゃんと話したい事が有るんだけど・・・良いかしら?」 テリーが頷くと、ビビアンは一番端のカウンターへとユナを案内した。 一番端の椅子に座らせられ、隣にビビアンも座る。 マスターが二人に飲み物を差し出してくれた。 「話って何ですか?」 ワケの分からないままユナから切り出すと 「さっき見て、分かってると思うけど・・・私、テリーの事が好きなの」 思いもよらなかった言葉に飲んでいたジュースが変な所へと入る。 「いきなり・・・何言って・・・」 ゲホゲホむせながら返した。本当にいきなりだった。 初対面の女の人にそんな事を言われても・・・。 「私、本気なの」 「へ、へぇ、そうなんですか・・・」 「へぇって・・・あなたもテリーの事好きなんでしょ?だから一緒に旅してるのよね」 なんで急にこんな事・・・。ユナはだんだんとうつむいた。 うつむいたままちらりとテリーを見るが、こっちには何の興味も示していない。 「ねぇ、テリーの事、好きなんでしょ?」 ますますユナはうつむいてしまった。 過去の事が頭をよぎる。 だが真摯に見つめるビビアンに嘘はつけなかった。 「・・・うん・・・・・・」 頷いて悲しそうに微笑んだ。 うわぁ・・・この子・・・。 ビビアンは不覚にも同じ女性相手にドキリと心臓が高鳴った。 以前話を聞いた時に、テリーと旅をしていたなんて”ユナ”と言う女性は よほどの美人なんだと思っていた。 だが実際は汚い旅人の服に、大きな剣、男のように短い髪と言う容姿に 心底からほっとしていたが、まじまじ顔を見てみると・・・ 案外綺麗に整った顔立ちに神秘的な瞳、不思議な雰囲気。 悔しくも一瞬見とれてしまった。 「でも・・・テリーはオレの事・・・」 「何・・・もしかして告白しちゃったの?」 ユナはまたテリーの方を向くと、思わず目が合ってしまったので慌てて視線を逸らした。 あー・・・・・・この子も本当に好きなんだなぁ・・・。 その様子を見て、何だかビビアンは違う意味で胸が切なくなってしまった。 ユナは真っ赤な顔でうつむいて、やっと答えた。 「うん・・・でも・・・ダメだったかな・・・」 「えっ、そっそうなの!?」 まさかホントに思いを伝えていたとは思わなかったので驚いて返す。 「でも・・・それで良くテリーと一緒にいられるわね・・・」 あ・・・いけない事聞いちゃったかしら・・・。 ビビアンは心の中で舌打ちすると、ユナはハハと呆れたように笑った。 「ホントにオレもそう思う。でもあいつには、借りが沢山有るから・・・。 今まで迷惑かけた分、少しは役に立ちたいと思ってるんだ」 ビビアンは、そんなユナに感心して、同時にいじらしく思えた。 その背中が寂しく見えてぎゅっと抱き締めてあげたかった。 マスターも手を休めて聞き入っている。 「あの、ビビアンさんはどうしてテリーを好きになったんですか?」 急にふられてビビアンは驚いた。 「え・・・っ?えーっと・・・どれぐらい前だったかしら・・・ 買い出しに行ってる途中、魔物に襲われてた所を偶然助けて貰ってね。 それから、なんて言うか・・・彼の事が頭から離れ無くって・・・。 数年経ってこの酒場で再会した時は運命だと思っちゃったわ。それがキッカケかしらね・・・」 「へぇ・・・そんな事が有ったんですか」 オレと同じだな。 ユナは心の中で思った。オレも、テリーに何度助けてもらったか。助けて貰う度にオレも・・・ 考えながら赤面する。またそれを吹き飛ばすかのようにブルブル顔を振った。 「頑張って下さいね!ビビアンさん」 もう、いいんだ。テリーの事は。 この気持ちは心に閉まっておこうと思ったじゃないか。側に居るだけで十分なんだ。 「そっ、そんな何言ってるのよ!一緒に頑張りましょうよ!」 最初は気迫十分で臨んだビビアンだったが、いつの間にかライバルを元気付けていた。 そうなってしまうほど、不思議な魅力がユナにはあった。 そんなビビアンにユナは有り難うの代わりに笑顔を返した。 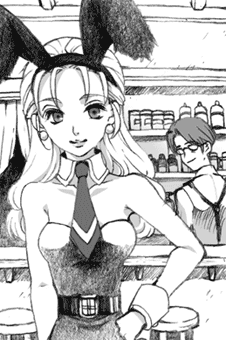 「あっ、もうこんな時間だ。オレ、宿に戻んなきゃ」 酒場に来てから、もう随分と時間が経過していたらしい。時間を忘れて話すとはこのことだろう。 テリーはもう既に酒場を後にしていた。 「凄く楽しかった。ありがとう、ビビアン」 頭を下げ、慌てて酒場を出ていった。と共にビビアンは大きなため息をつく。 「・・・・・・テリー君を絶対譲らないって言ってたのは、何処の誰だったかなー・・・」 マスターが口笛を吹きながらボトルを直している。 「マスターのいじわるー」 ビビアンは怪訝な顔で頬を膨らませ、グラスの酒を飲み干した。 「まぁ分からなくもないけどね、ビビアンちゃんの気持ちは・・・」 酒瓶を空になったグラスに傾ける。 「そうなのよ・・・すっごくいい子なのよあの子・・・」 赤い葡萄酒がグラスに注ぎ込まれるのを見つめながら ビビアンは小さく呟いた。 「なんであんな子、振っちゃうんだろう・・・テリー・・・」 「やっぱりテリー君だからじゃない?」 マスターは意味ありげな言葉で答えた。 「どういう事?それって・・・」 不審な顔で見つめ返す。 「テリー君の頭の中には、最強の剣の事しか無いって事さ」 「・・・マスター・・・それは私に諦めろって事?」 「そうだね、ビビアンちゃんの頑張り次第かな」 マスターはそう返すと、これ以上ビビアンの追撃を受けないよう そそくさと店の奥へと引っ込んだ。 ビビアンはため息を零して、つがれた酒をひとくち口に含んだ。 やっぱり、テリーの心には誰も入ることって出来ないのかな・・・。 あれだけ最強の剣や最強の強さにこだわるんだもの、女の事なんて考える暇無いわよね・・・。 ビビアンは色々な思考を張り巡らせつつ 届かない想いを胸の中に感じて息苦しくなっていった。 「テリー・・・?」 宿に帰ってすぐ、ユナはテリーの部屋のドアをノックした。 反応は何もない。鍵の掛かっていないドアを開けてキョロキョロと見回す。と、その人はそこにいた。 「もう夕食、食べたのか?」 ・・・・・・テリーに反応は無い。目を伏せたままベッドに仰向けになり、足を組んでいる。 「なぁ、テリー」 再び問いかけても反応はない。ふと耳を澄ますと、気持ちの良さそうな寝息が聞こえてきた。 「なーんだ、寝てたのか」 聞こえていないと知りながら、膝をついてベッドに顔を伏せた。 ・・・テリーのにおいだ。この間おぶってもらった時と同じ。 何か眠くなってしまいそうな心地良い・・・・・・ ベッドの上に脱ぎ捨てられた帽子が目に入った。 出会ってすぐの頃にレイドックで作った、何とも不格好な帽子・・・・・・だ。 「ずっと持っててくれたんだ」 ユナは嬉しくなって微笑むと、その帽子を持って立ち上がった。 同時に、テリーへの想いが溢れんばかりに込み上げてくる。 目を伏せてぎゅっと帽子を抱き締めた。 「・・・・・・」 ユナはその想いにどうして良いのか分からなくなって 帽子を戻すと、たまらず部屋を出ていった。 ガタガタと階段を下りていく音が聞こえるとむくっと何かの影が見える。 「・・・・・・行ったか・・・」 月の光が部屋の窓から差し込んで、銀髪の少年を優しく照らしていた。 ユナは夕食を食べ終わると何となく宿屋を出た。 サンマリーノの街を、久しぶりに歩きたかったから・・・。 「・・・何処に行くんだ?」 聞き慣れた声が後ろから聞こえ、ガバッと振り向く。 テリーだった。 「えっ!・・・いや・・・何か、眠れなくって」 必要以上に緊張している。テリーは隣に来て 「久し振りに気が合うな。オレもだ」 どういう風の吹き回しなのだろうか、ユナと一緒に歩き出した。 静まりかえっているはずの夜でさえ、サンマリーノは賑わっていた。 消える事のない街の明かりが若者たちの心を躍らせている。 カジノから賑やかな光、酒場からは賑やかな声、 光の届かない薄暗い道の端には、男と女が熱い抱擁をしていた。 ユナはそれらを必死に見ないように歩く。 二人はサンマリーノ時計塔広場のベンチに腰を下ろした。少し距離をとって。 「好きだよ・・・・・・」 「私もよ・・・」 向かいのベンチに座っている男女が抱き合って愛の言葉を囁き有っていた。 ああーー!もう、オレのバカ!! テリーが隣にいるモンだから緊張してこんな所に来ちまった! どうしようどうしよう急に場所変えるのもアレだし、テリーはそんなに気にしてないかもしれないし・・・ 平静を装っているつもりの外面とはヨソに、心の中では悶え打ってしまっている。 目のやり場に困ってしまったユナは、真っ赤な顔でうつむいてしまった。 「いつマウントスノーに向かうんだ」 「船が有り次第だな」 なんとか切り出した言葉だったがテリーは一言で返す。 こんなに早くに会話を終わらせるなよ・・・。 目の前の男女は抱きしめ合いながら濃厚なキスをしていた。 オイオイ・・・。せめてもうちょっと人目の付かない所でやれよ・・・。 ユナは益々うつむいた。 「・・・場所・・・変えるか?」 真っ赤な顔のままテリーを見た。 「本当に今日は気が合うな」 元気良く返して一目散に立ち上がる。 テリーはふっと笑みを浮かべ、ベンチから立ち上がって歩き出した。 夜道をしばらく歩いて 「案外、純情な奴なんだな。キスぐらいで」 「なっ!」 歩きながら、テリーの言葉にユナはまた顔を赤らめた。 「あっ、あっ、あったりまえだろ!!オレ・・・そんな・・・まだ、キ、キスなんてしたことないんだし・・・」 そうだ。初めて一緒に旅したのもテリーだし。初めて好きになった男もテリーなのだ。 「まぁ・・・それはそうだろう。色恋沙汰には縁がなさそうだからなお前は」 頷いて一人納得している。 「・・・なんだよ。そーゆー自分は経験あるのかよ?」 テリーにこんな事聞くのも恐ろしいのだが このまま自分だけいじめられるのも悔しいので聞いてみた。 「さぁな」 「さぁなって、答えになってないよ」 「忘れた」 忘れたって事は、忘れるぐらいやったのか!? いや、テリーならあり得るかも・・・そう思い口を開いた瞬間。 「二人で何、楽しそうにじゃれあってるのよー」 ハっとして声の方を振り向く。バニー姿のビビアンだった。 「酒場、寄っていくわよね?」 ビビアンに無理矢理連れられ、二人は酒場に入った。 夜の酒場は仕事帰りの船乗りたちや旅人で溢れんばかりに賑わっていた。 「オイ、忙しいんじゃ無いのか?」 ビビアンの方を見ると、テリーははっとした。珍しく悲しそうな瞳。 「テリーの事だから明日になったら、もうサンマリーノから出ていっちゃうんでしょ? ・・・お願い・・・少しでも一緒にいたいの・・・」 見つめ合っている二人に、ユナは胸が詰まるような思いがした。 「ユーナっ!」 ふいに名前を呼ばれる。 「頼みたいことがあるんだけど・・・いいかしら?」 「?」 「ちょっと待てよ!こんな格好で人前に出るのか!?」 酒場の奥の部屋から出てきたユナの格好は・・・バニーガール。 「一生のお願いよ!テリーとゆっくり話がしたいの! それに・・・今日は一緒にいたいの・・・いいでしょ?」 手を合わせて頭を下げるビビアンにあきらめて肩をすくめる。 「・・・今日一日だけだからな」 「ありがとうユナっ!」 抱きつくビビアンにそっと耳打ちする。 「頑張れよ、ビビアン」 ぽんっと肩をたたいてはにかんだ。 またビビアンはユナをぎゅっと抱き締めた。 テリーとビビアンが酒場から出るのを見届けると、マスターがユナを呼んだ。 「早速なんだけどユナちゃん。コレ、窓際のテーブルにもってってくれる?」 「あ、はい」 ユナは言われたとおりにトレイに乗せて気をつけながら酒のボトルとグラスを運ぶ。 「おっ、新しく入った子かい?」 「はっ、はぁ?オ・・・私の事ですか?」 「可愛いね〜。名前はなんて言うの?」 「えっ!あ・・・ユ、ユナです・・・」 初めてだぜ。こんなに普通に話しかけられたのは。いつも怪訝な目か不審な目か バカにされた目でしか見られたこと無かったし・・・。 そうか。バニーの格好をしているオレは今!普通の街娘として見られてるのか! 「オイ!!そこの女!!酒はまだか!?待ってるんだよ!!」 「ああっ!はいっ!!」 精一杯の営業スマイルで仕事をこなす。 ビビアン・・・上手くやってるかなぁ。 先ほどユナとテリーが腰掛けたベンチに二人は腰掛けた。 「話って何なんだ?」 まずテリーが切り出した。 「好きなの」 とてもストレートにビビアンは自分の想いを告げた。テリーは何も言わずに黙ったままだった。 「・・・振るんなら思い切り振ってよね!でないと、私、先に進めないから」 沈黙に耐えかねて、テリーの腕を掴んだ。アメシストの瞳に自分が映る。 ドキっとビビアンは反応した。 「悪い・・・・・・お前の気持ちに応える事は出来ない」 まっすぐに見つめてそう返す。 二人の間に冷たい夜風が吹き抜けた。 「・・・や・・・やっぱりだわー、本当に、期待を裏切らないのねー テリーなら、絶対そう言うと思ってた・・・」 ぽたり。ビビアンの頬に何かが伝わった。 一筋、顔の輪郭を辿ると堰を切ったように両目から溢れてきた。 「何・・・・・・期待してたんだろ・・・私・・・。テリーの気持ちは、知ってたのに・・・」 だんだんと声が震える。 テリーはビビアンの頬に手を当てて涙を拭きあげた。 ビビアンはたまらずその想い人の胸に顔を埋める。 「・・・最強の剣しか頭に無いの?それ以外の物は必要ないの・・・?女なんて邪魔なだけなの?」 テリーは答えなかった。再び沈黙が続くと 「・・・ごめん、変な事言って。らしくないわよね」 テリーから距離をとると、いつの間にかいつものビビアンに戻っていた。赤くなった瞳以外は。 「ビビアン・・・」 「ん。有り難うテリー。思いっきり振ってくれて。これで私、先に進める。 もっといい女になって、振った事を後悔させてあげるからね」 ベンチから立ち上がると、無理な笑顔を作って酒場へと踵を返した。 「ご苦労様。ユナちゃん」 「うっ・・・疲れた・・・ビビアンって毎日これやってるって凄いな」 ようやく客足が途絶えて一休みする事が出来た。 接客がこれほど精神的に疲れるもんだったとは、初めて知った。 マスターは労いの言葉を掛けた後、ユナの為に飲み物を作ってくれる。 カウンターに座ってダウンした後、出してくれた飲み物をありがたく飲んだ。 やっと余裕が持てると、気になって仕方ない事を思い出す。 ・・・いつになったら帰ってくるんだろう・・・ 「気になるかい?テリー君とビビアンちゃんが・・・」 ユナは否定する事も無いと思い、素直に頷いた。ちょうどその時。 「ただいま〜。ご苦労だったわね、ユナ」 普段着のビビアンが声と共に店のドアを開けた。後からテリーも入ってくる。 「いや、凄く疲れたよ・・・本当・・・」 「そうでしょ、そうでしょー。私、毎日これやってるんだからー」 上半身をカウンターに預けてしまっているユナの肩をぽんっと叩いて隣に座る。 二人から椅子2つ分空けた場所にテリーも座った。 「旅立ったら、もうこの街に来ることはないの?」 「そんな事は無いと思うけど・・・」 ビビアンの問いかけに答えた後、テリーを見た。 向こうは本当に興味がなさそうに店内に飾られていたサンマリーノ周辺の地図を見ていた。 『女泣かせな奴・・・』 二人は同時にそう思って、同時にグラスを空にした。
|